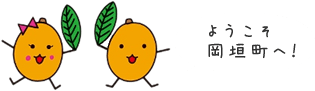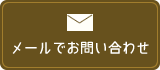世帯の所得に応じた軽減(申請不要)
前年中の所得額が一定基準以下の世帯は、均等割額(一人あたり)及び平等割額(一世帯あたり)が軽減されます。
- 7割軽減
世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯に属する被保険者の所得の合計が
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 - 5割軽減
世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯に属する被保険者の所得の合計が
43万円 + 30.5万円 ×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 - 2割軽減
世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯に属する被保険者の所得の合計が
43万円 + 56万円 ×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
注:給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人です。
特定世帯の軽減(申請不要)
これまで国民健康保険の被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
このとき、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、4分の1を軽減(4分の3を課税)されます。
ただし、世帯構成が変わると対象外になるときがあります。
未就学児被保険者の減額(申請不要)
未就学児(小学校入学前の子ども)がいる世帯に対して、一律に「未就学児の均等割額の2分の1」を減額します。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した人の軽減(申請が必要です)
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した人の国民健康保険税を届出により軽減します。
対象
次の全てに当てはまる人
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である
- 離職日時点で65歳未満である
- 雇用保険の失業給付を受けている(船員保険法の給付受給者は対象外)
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかに当てはまる 注:「雇用保険特例受給資格者証」と「雇用保険高年齢受給資格者証」は対象外
- 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)
- 23、33、34(特定理由離職者)
軽減額
離職した本人の前年の給与所得を、100分の30とみなして計算します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで軽減されます。
軽減措置の手続き
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。
健康づくり課医療年金係で申請してください。
申請が遅れた場合でも、離職日までさかのぼって軽減します。
社会保険等の被扶養者であった人の減免(申請が必要です)
平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されたことで、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。そのため、会社の健康保険などに加入している人が75歳になると、被扶養者も、それまでの社会保険の資格を喪失します。
このことを理由に、国民健康保険に加入した65歳以上の人(旧被扶養者)は、次のとおり保険税を減免します。
対象
国民健康保険の被保険者のうち、次の全てに当てはまる人
- 国民健康保険の資格を取得した日時点で、65歳以上である
- 国民健康保険の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった
- 国民健康保険の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入した
減免措置の額
- 所得割額 全額
- 均等割額 最大半額(均等割額が7割軽減、5割軽減されている場合を除く)
- 平等割額 最大半額(平等割額が7割軽減、5割軽減されている場合を除く)
減免措置の手続き
この減免措置を受けるためには、国保加入時に申請が必要です。
手続きに関する質問、相談、申請などは、健康づくり課医療年金係まで問い合わせてください。
産前産後期間相当分の減額(申請が必要です)
出産予定または出産した国民健康保険加入者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額します。
対象
国民健康保険に加入している人で、妊娠85日(4カ月)以降に出産した人(死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産を含む)
対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
注:多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
| 3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産予定月 | 1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単胎妊娠 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 多胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
注:表中の記号「〇」は「該当月」、「×」は「非該当月」を表します。
免除額
対象期間相当分の所得割額と均等割額の全額
減額措置の手続き
下の関連ファイルにある「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」を健康づくり課医療年金係に提出してください。
出産予定または出産日が確認できるもの、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるものが必要です(母子健康手帳、出生証明書等)。
注:出産予定日の6カ月前から届け出をすることができます。